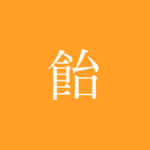底なし穴に落ちる夏(2023.7.6)
ame
線香花火に照らされている彼女の顔が知らない人のように見えた。別次元の存在ではないかとさえ思える。見慣れない浴衣のせいだろうか。少し腕を伸ばせば肩にも髪にも、頬にさえ触れられる距離にいるというのに。
火花散るリズムに合わせて明暗が変化し、不可思議な世界に迷い込んだ気分になる。
こんな気持ち知らない。不安で不安でしかたがない。足元が崩れていくみたいで心細い。
彼女の手元でパチパチと小さな音を立てながら、しかし激しい火花を散らす線香花火は、やがて大きな玉となり、瞬く間に――。
「落ちちゃった」
彼女の声を合図に、辺りが急激に暗くなった。そんな気がしただけかもしれない。少し離れた場所にランタンを置いてあるのだから、たかだか線香花火一つ消えたところで周囲の光量に支障はないはず。
それでも。シンと静まりかえった空間は、とても暗く思えた。
真隣にいる人しか、見えなくなるくらいに。
「どうしたの? なんだか顔色悪くない?」
こちらを覗きこむ丸い目。垂れ眉がいっそう垂れている。
白くてなめらかな肌をした手がこちらへ向かい、そのまま額にあてがわれた。夏だというのに冷たい指先。
彼女が動くたび、まとう浴衣の袖がずり下がっていく。肘が、二の腕があらわになる。
静かだったはずの空間に爆音が響き渡った。他の誰にも、すぐそばの彼女にすら聞こえていないだろうが、全身を打ち鳴らすそれはあまりに煩さくて、自然と顔が歪んでいく。
「ねえ、大丈夫?」
先ほどよりも気遣った声と手つきが、ひどく、たまらない。
「……大丈夫」
目を逸らし、そっと彼女の手を押し戻す。
今、キミはどんな顔をしている? 気になるのに直視できない。
「そう?」と尚も心配している声がして、腹の底がざわついた。
ああ、このままだと、全てが終わる予感がする。
「念のため向こうで休んでくるよ。気にせず続けてて」
「……ん、わかった。無理しないでね」
頷き、即座に立ち上がる。危うくよろけるところだったが、なんとか脚に力を入れて踏ん張った。
一歩踏み出す足が重い。重力が何倍にもなったのかと思った。それでも「離れなければ」という一心で歩いた。
心臓が痛い。シャツ越しに胸元を力一杯握りしめても、内側の痛みは消えてくれない。
不安と期待と焦燥と。あらゆるものが腹の中で混ざり合いうごめいている。胃を揉まれているみたいな不快感で吐き気がした。
こんなの、同級生が話していたのとはまるで違う。全然いいものなんかじゃない。キラキラと煌めくようなものじゃない。
こんなのは、まるで、底なしの穴に突き落とされたみたいだ。
*横スクロールで読めます